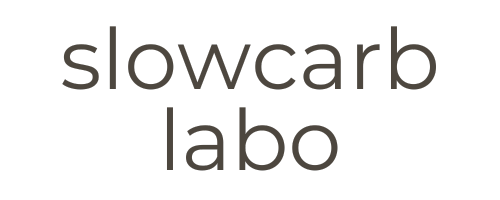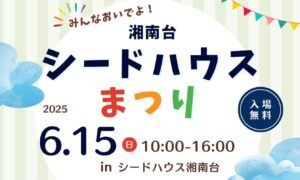ナースヘルススタディから読み解く「血糖値コントロールの未来」
こんにちは。管理栄養士の原なみです。
先日、妊娠糖尿病学会に参加してきました。その中で紹介された「ナースヘルススタディ(Nurses’ Health Study)」の最新報告がとても有益だったので、今日はその内容を皆さんとシェアしたいと思います。
妊娠糖尿病を経験された方、血糖値が気になる方、糖尿病予防に関心がある方にとって、食事が私たちの未来を変える鍵になる。そんな希望が持てる内容でした。研究の対象は妊娠糖尿病の方ですが、血糖コントロールに関しては誰にでも関係のある内容です。
ぜひ最後までご覧ください。
ナースヘルススタディって何?
「ナースヘルススタディ」は、ハーバード大学の公衆衛生大学院が中心となって行われている40年以上続く大規模な疫学研究です。疫学研究というのは、「生活習慣と病気の関係を、たくさんの人のデータから探る研究」の事。
1976年にスタートし、看護師を中心に10万人規模の女性を対象に、生活習慣と病気の関係を長期にわたって追跡している研究です。
この研究の特徴は、「同じ人たちを長い間追いかけて調べている」という点です。
こうした調査は「コホート研究」と呼ばれ、時間をかけて生活習慣と病気の関係を詳しく見ていくことで、どんな習慣が病気の予防につながるのかが、よりはっきりとわかってきます。
そのため、世界中の専門家が参考にしている、とても信頼性の高い研究なんです。
今回ご紹介するのは、その「ナースヘルススタディⅡ」で収集されたデータをもとに、「妊娠糖尿病の経験がある女性」が将来糖尿病になるリスクと、食事パターンによる予防の可能性を検討した研究です。

妊娠糖尿病とは?
妊娠糖尿病とは、妊娠中に初めて発見・診断される血糖値の異常のことです。妊娠中は胎盤から分泌されるホルモンの影響で、インスリン(血糖値を下げるホルモン)の働きが妨げられやすくなります。そのため、血糖値が通常よりも上がりやすく、下がりにくい状態になります。
妊娠糖尿病と診断されると、食事管理や運動療法をはじめ、場合によってはインスリン注射が必要になることもあり、妊娠中はとても厳しい血糖値コントロールが求められます。
これは母体だけでなく、赤ちゃんにも影響があるためです。血糖値が高い状態が続くと、巨大児、早産、帝王切開率の上昇などの分娩時合併症のリスクが高まることが報告されています。
多くの方は出産と同時に血糖値が正常に戻るため、「妊娠中だけの一時的なこと」と思われがちですが、実はそうではありません。
妊娠糖尿病を経験した女性は、将来2型糖尿病を発症するリスクが高くなることがわかっています。そのリスクは 約5倍以上 と言われており、予防や対策が必要なのです。
しかし現実には、妊娠中は医療機関で管理されていても、出産後にはフォローアップや予防の取り組みがされないまま放置されてしまうケースが多く見られます。この「見過ごされがちなリスク」が、将来の健康を大きく左右する可能性があるのです。

「私は妊娠糖尿病じゃなかったから関係ない」と思っていませんか?
実は、妊娠糖尿病と診断されなかった方でも、この研究結果は無関係ではありません。
なぜなら、妊娠中に見られるインスリン抵抗性(インスリンの効きが悪くなり、血糖値が上がりやすくなる状態)は、糖尿病予備軍や糖尿病の方にも共通する体の特徴だからです。
妊娠中はホルモンの影響で自然にインスリン抵抗性が高まりますが、この「血糖値が下がりにくい体質」は、糖尿病発症直前の状態と非常によく似ています。
そして、これは女性にとって特に知っておきたいポイントです。というのも、妊娠糖尿病のときに見られるインスリン抵抗性は、生理前にも起きる自然な体の反応と似ているからです。
生理前(黄体期)は、妊娠に備えてエネルギーをため込みやすくなるため、ホルモンの影響でインスリンの働きが一時的に弱まり、血糖値が少し上がりやすくなります。ただしこの変化は一時的で、生理が始まると元に戻ります。一方、妊娠糖尿病の場合はこの状態がより強く、長く続くのが特徴です。
つまり、妊娠糖尿病は特別な病気ではなく、女性の体に本来備わっている自然な仕組みが少し強く出すぎてしまった状態ともいえるのです。
ですから、妊娠糖尿病でなかったとしても、「糖尿病ではないけれど食後の血糖値が高めに出る」「家族に糖尿病の人がいる」「体重増加が気になる」などの方は、すでに軽度のインスリン抵抗性を抱えている可能性があります。
この研究が示す「食事による予防の効果」は、まさにそうした方々にも役立つ内容です。インスリン抵抗性を持つすべての人にとって、この研究データは生活習慣を見直す大きなヒントになります。
将来の糖尿病リスク、どうしたら減らせる?
今回紹介する研究は、1989年から2011年までの長期にわたる追跡調査に基づいており、ナースヘルススタディIIの参加者の中から、妊娠糖尿病の既往歴がある女性を対象に行われました。
注目すべきは、健康的な食事パターン(地中海食・DASH食・AHEI)や適正な体重管理、定期的な運動、禁煙、飲酒の調整といった健康習慣をバランスよく実践していた女性たちが、そうでない人たちに比べて2型糖尿病の発症リスクを約40〜57%低く抑えられていたという結果です。
さらにこの研究では、たとえ過体重であったり、遺伝的に糖尿病リスクが高い女性であっても、リスク要因を一つずつ改善することによって、発症リスクをさらに下げることができたと報告されています。
これは「完璧な生活習慣を目指しましょう」という話ではありません。今できることを少しずつ取り入れ、自分にとって心地よく続けられるバランスを探していく。その積み重ねが、将来の糖尿病リスクを確実に下げていくことにつながります。
どんな食事がリスクを減らしたのか
研究で効果があるとされた食事パターンは主に以下の3つです
1. 地中海式食事(Mediterranean Diet)
- オリーブオイル、ナッツ類などの良質な脂質
- 魚介類、豆類、野菜、果物を豊富に含む
- 赤身肉は控えめ、精製された糖質は少なめ
- リスク低下率:約57%

2. DASH食(Dietary Approaches to Stop Hypertension)
- 高血圧予防のための食事パターン
- 野菜、果物、低脂肪乳製品、全粒穀物が中心
- ナトリウム(塩分)や飽和脂肪酸が少なく、血管にやさしい
- リスク低下率:約54%

3. AHEI(Alternative Healthy Eating Index)
- ハーバード公衆衛生大学院が作成した食事の質評価指標
- 野菜や果物、全粒穀物、ナッツ、魚、豆などを推奨
- 加工肉や砂糖入り飲料は控える
- リスク低下率:約48%
どの食事法にも共通しているのは、「自然に近い食品を多く、加工食品を少なく」ということです。無理な糖質制限や極端なダイエットではなく、持続可能な食生活こそが鍵となります。
ここで注意したいのは、これは海外の研究だということです。日本の食文化とは異なりますが、日本の伝統的な和食にも、野菜・豆類・魚・発酵食品など、共通する要素がたくさんあります。各食事パターンについては、またのブログで詳しく紹介しますね。
実は、極端な制限をしなくても、リスクを下げる食品をうまく取り入れることで、将来の糖尿病はしっかり予防できるのです。
無理な糖質制限は逆に糖尿病発症のリスクをあげる事もある
糖質は私たちの体にとって大切なエネルギー源でもあります。重要なのは、その「質」と「組み合わせ」です。たとえば、野菜やたんぱく質と一緒に炭水化物を摂ることで、血糖値の急上昇を防ぐことができます。
また、精製された白い炭水化物(白米や白パン)ではなく、玄米や全粒粉パン、大麦などの「未精製の炭水化物」を選ぶことも糖尿病予防には効果的です。
ナースヘルススタディの他の報告でも、炭水化物を含めた食事全体の「質」が大切であり、低炭水化物食(糖質制限)をとる場合でも、その代わりに摂る食品が何であるかが重要とされています。
さらに注意したいのは、糖質を減らす代わりに動物性たんぱく質や動物性脂質を多く摂る食事です。ナースヘルススタディの別の研究では、動物性脂肪が多い食事はむしろ糖尿病の発症リスクを高める可能性があるとされています。
逆に、植物性のたんぱく質や脂質を中心とした低炭水化物食では、糖尿病リスクが下がるという報告もあります。
ここで伝えたいのは、「糖質を減らせば健康になる」という単純な話ではないということです。肉や脂質を好きなだけ摂っていいという誤解された糖質制限には、リスクがあるのです。
ただし、「すべて植物性が正解」というわけでもありません。
私たちの体は一人ひとり違います。だからこそ、大切なのは「自分に合った適量」を知ることです。毎日の食事の選び方が、明日の自分の体をつくります。健康な未来は、日々の積み重ねの中にあるのです。
食や健康の情報は日々アップデートされています。だからこそ、私たちも学び続けることが大切です。「今の自分」に合った選択ができるように、これからも最新の情報をシェアしていきますね。
次のブログは学会報告第2弾『空腹で糖尿病??検査前に知っておきたい意外な落とし穴』をお届けします。
【参考文献】
- Nurses’ Health Study 公式サイト:https://nurseshealthstudy.org
- 第41回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会